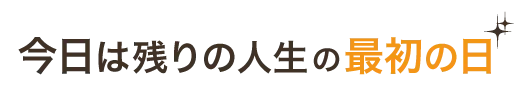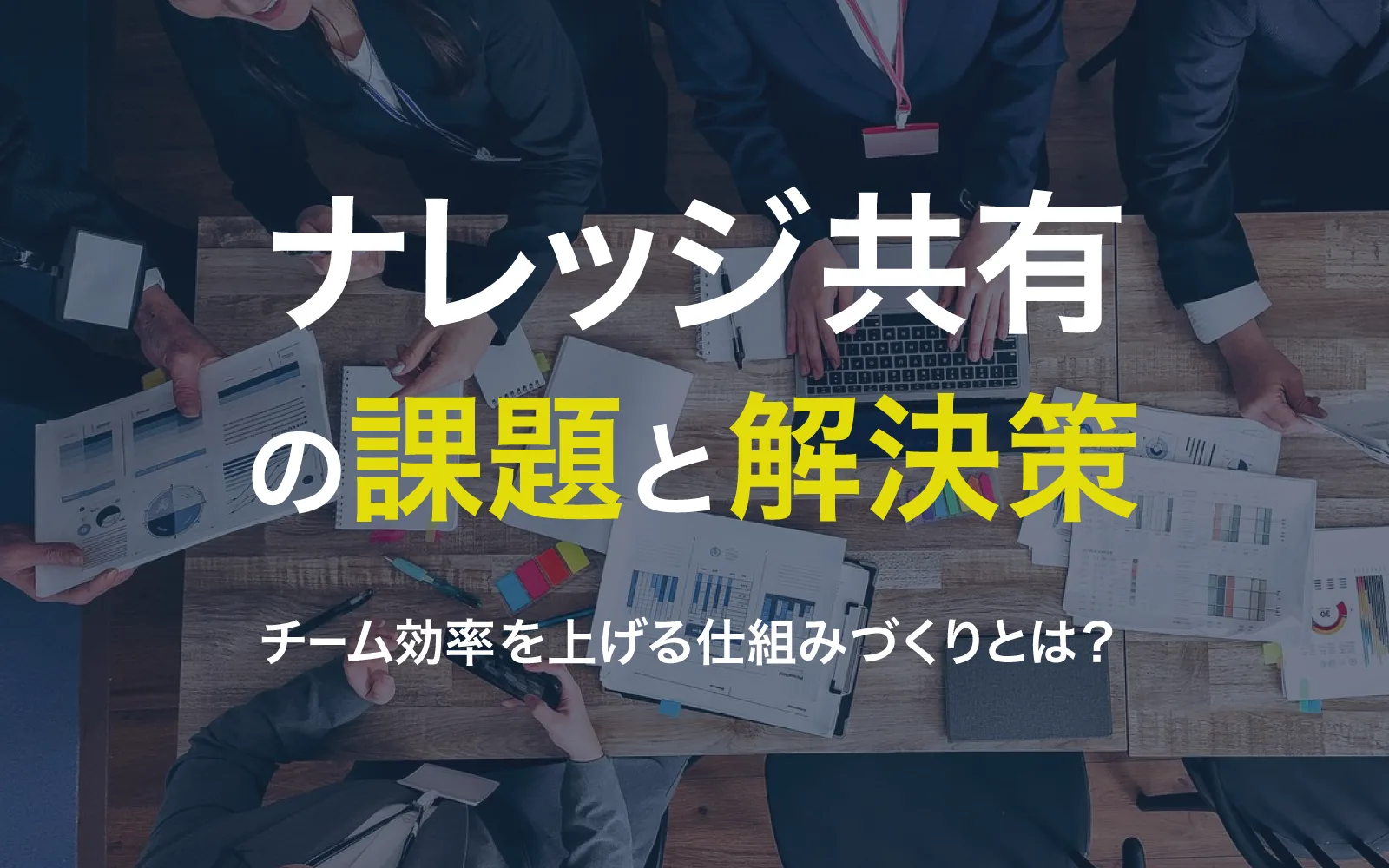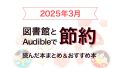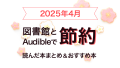チームのマネジメントをしていると、「もっと効率よく仕事が進むはずなのに」と感じる場面に出くわします。それは、個々のメンバーが持つ知識や工夫が十分に活用されていないときです。
特に、ナレッジの共有は大きな課題です。それぞれが持つ経験や知見は貴重な財産でありながら、個人にとどまってしまい、チーム全体の成長やプロジェクトの効率化に結びついていないことがあります。これをうまく活用できれば、チーム全体のパフォーマンスを向上させることができると考えています。
この記事では、ナレッジ共有の重要性と、これまで取り組んできた試行錯誤、そして現在実践している方法について詳しくお伝えします。
ナレッジ共有が必要な背景
まず、ナレッジ共有を考えるきっかけとなった課題についてお話しします。日々の業務の中で、次のような問題が浮き彫りになりました。
業務の非効率化
チーム内で、過去に行った競合調査や他のメンバーが実施した調査を再度行う場面が多々見受けられます。このような重複作業が続くと、貴重な時間やリソースが無駄になり、業務の非効率化につながってしまいます。
たとえば、日付選択のUIに関する調査を別のメンバーが実施していたケースがあります。このような調査は、プロジェクトの要件によって一部変更が必要な場合もありますが、多くの競合調査内容は共通しているはずです。
もし、過去の調査結果や他のメンバーが行った作業内容をスムーズに参照できる仕組みが整っていれば、無駄な作業を減らし、次のステップへ迅速に進むことが可能になります。
知識の属人化
各メンバーが持つノウハウや工夫が、個人の中に留まってしまうケースは少なくありません。他のプロジェクトでも応用可能な優れたアイデアが共有されないことで、チーム全体の成長機会を失うことがあります。
たとえば、プロジェクトで合宿を行った際に準備した項目や進行方法、結果を踏まえた反省点。また、アンケートを実施した際の設問内容や周知の方法などには、他のプロジェクトでも活用可能な貴重な情報が含まれています。
しかし、こうしたナレッジを適切に共有する仕組みがなければ、チーム全体でその価値を活かすことはできません。
個人レベルではスキルアップにつながりますが、チームマネージャーとしては、これらのナレッジを共有し、チーム全体の力を底上げすることが重要です。共有を通じて、個人の知見がチーム全体の成果として発揮される環境を作りたいと考えています。
ナレッジ共有の試行錯誤
ナレッジ共有を推進するために、これまでいくつかの取り組みを実施しましたが、その中でさまざまな課題が浮き彫りになりました。ここでは、それぞれの試行錯誤について詳しくお話しします。
半年に一度のナレッジ共有会
部署全体でナレッジを発表する場を設けました。この場は半年に一度開催され、ノウハウや工夫を共有することを目的としていました。
この取り組みにより、これまで日の目を見なかったナレッジが部全体で共有される機会が生まれ、新しい視点やアイデアが広がる効果もありました。
しかし、この形式には以下のような課題がありました。
- 準備コストの高さ
発表内容の準備には多大な時間と労力が必要でした。特に、内容を体系的に整理する過程や資料作成に負担を感じるメンバーが多く、その結果、ナレッジ共有のハードルが高くなってしまいました。また、運営側にとっても、共有の場を設けたり時間を確保するなど、定常的でないため都度コストがかかっていました。 - 活用されづらい共有情報
発表されたナレッジが、その後の業務で適切に活用される機会が少ないという問題もありました。主な原因としては、ナレッジ共有の頻度が低いため、共有された情報を活用するタイミングが遅れてしまうことが挙げられます。また、発表された内容がどこに保存されているのかが不明確であるため、せっかく共有された貴重な知識が埋もれてしまい、必要なときにすぐにアクセスできないという状況も発生しました。
Slackを活用したナレッジ共有
Slack内に専用のナレッジ共有チャンネルを設け、メンバーが気づいたナレッジを自由に投稿できる仕組みを導入しました。
これにより、ナレッジ共有会を待たずに、日々の業務で得た知見をすぐに共有することが可能となり、ナレッジ会では時間の関係で共有しきれなかった情報も手軽にシェアできるようになりました。
しかし、この方法にもいくつかの課題がありました。
- 投稿が一部の人に偏る
ナレッジ共有の意識が高いメンバーに投稿が集中し、全体としての共有量が偏ってしまいました。また、一部のメンバーは自分の持つ知識がナレッジとして価値があることに気づいておらず、その場合はチームマネージャーがヒアリングを行い、投稿を促す必要がありました。これにより、チームマネージャー側の負担が増加しました。 - 情報の粒度のばらつき
投稿内容に詳細さや統一感が欠けることが問題となりました。テンプレートを導入して粒度を揃えようとしましたが、「テンプレートを使うことで共有のハードルが上がる」といったフィードバックがあり、使いやすさとのバランスに課題が残りました。 - ドキュメントへのリンクの難しさ
投稿内容にドキュメントへのリンクが含まれる場合、それを読むために別途コストがかかるという問題も発生しました。リンク先の内容を確認する手間が多いと、ナレッジが活用されにくくなることが分かりました。 - 促す人がいないと定着は難しい
ナレッジ共有には、各メンバーの主体的な参加が求められます。強いモチベーションがないと、自発的に投稿することが難しく、定着が困難な点が課題となりました。
調査結果へのハブページを作成
これは、上記の2つの施策とは異なり、「調査結果を繰り返し調査しない」という課題に焦点を当てた取り組みです。
これまで、各プロジェクトで調査結果を個別にまとめていたため、調査結果を参照するには各プロジェクトのドキュメントを探さなければなりませんでした。また、特定のプロジェクトで調査が行われていることを知らなければ、その調査結果を活用すること自体ができませんでした。
そこで、調査結果を一元化したハブページを作成し、結果にアクセスしやすくしました。これにより、情報へのアクセス性が向上し、必要な調査結果を迅速に参照できるようになりました。
しかし、この方法にも以下のような課題が発生しました。
- ハブページが見つけられない
ハブページがどこにあるかを探すのに手間がかかり、最初のアクセスに時間を要しました。そのため、活用すべき場面でハブページの存在を忘れられ、結果的に活用されない事態が発生しました。 - 運用されない
チームメンバーは主にプロジェクトに注力しているため、新たな調査結果が作成されても、そのリンクをハブページに反映する作業が行われないことが多く、ページが更新されず、情報が陳腐化するリスクがありました。
現在の取り組み:効果的なナレッジ共有の仕組み
これまでの試行錯誤を経て、現在はより効果的なナレッジ共有の仕組みを構築しています。
まだ改善の余地はありますが、仕組みを整えることで運用コストが低減し、その効果は着実に向上しています。
具体的には、以下の取り組みを実施しています。
頻度を上げる:毎週のチーム定例会でのナレッジ共有
ナレッジ共有の頻度を高めるため、チーム定例会を活用し、毎週ナレッジ共有の時間を設けています。定期的に情報を共有することで、重要な知識が埋もれることなく、日常的に活用されるようになり、チーム全体の情報の流れがスムーズに進むようになりました。
頻度が高いため、大きなナレッジだけでなく、細かなナレッジも活発に共有されています。
口頭での共有により、理解が難しい場合は質問を受け付け、すぐに活用できる状態にしています。そのため、Slackで共有されていた際のような、わざわざ文章を読む手間を省くことができます。
チーム定例会のアジェンダにナレッジ共有を組み込むことで、促す人がいなくても定期的に実施できる仕組みが整い、部署のナレッジ共有会で必要だった運営側の準備コストが不要になりました。
参照先を定める:「ナレッジを溜める場所」の作成
思いついたナレッジはすぐに書き留め、共有できる場所を作成しました。
これには、miroを活用しています。専用のmiroボードを作成し、チーム定例会で毎週確認しています。新たなナレッジがあれば、その場で共有してもらっています。
また、チーム定例会で共有した内容は、同じmiroボード内でジャンルごとに分類して整理し、後から参照しやすくしています。
ナレッジを共有したいと思ったときには、miroにアクセスすれば簡単に見つけられますし、過去に共有された情報を思い出したときも、同じmiroボードで確認できます。さらに、課題を感じた際に「これに関するナレッジがなかったかな?」と思い立ったときにも、miroで調べることができます。
これにより、必要な情報に誰もがすぐアクセスでき、ナレッジがどこに保存されているか分からない、または忘れてしまうことがなくなり、チーム全体で無駄なく活用できる仕組みが整いました。
ナレッジを吸い上げる:「無意識のナレッジ」を発掘する工夫
メンバーは、自分の持つ知識がナレッジとして価値があることに気づいていないという課題がありました。この問題を解決するため、現在進行中のプロジェクトで行っていることをメンバーに詳細に共有してもらう工夫をしています。
具体的には、画面共有を行い、作成しているものや取り組み、課題についてその場で共有してもらいます。その後、質問や感想を話す時間を設け、共有された情報を深めます。
この方法により、チーム全員で解決策を模索することができ、ナレッジとして蓄積されるだけでなく、同時にチームの課題認識も共有され、問題解決がスムーズに進むようになっています。
ナレッジ共有の成果と今後の課題
現状の成果
ナレッジ共有の仕組みを強化した結果、チーム全体でのナレッジ活用が進み、業務の効率化が実現しました。特に、過去の経験や学びがスムーズに活用されることで、同じ調査や作業を繰り返すことが減少し、時間とリソースの無駄を削減できました。
また、属人化の解消に向けて、メンバー間で知識の共有に対する意識改革が進行中であり、個々のノウハウがチーム全体の強みとして活用されつつあります。
残る課題
現在、毎週のプロジェクト定例会でナレッジを共有していますが、発表の準備に時間と手間がかかることが課題です。発表内容の整理や準備は以前の部署でのナレッジ共有会と比べるとコストは低減していますが、メンバーにはプロジェクト改善に集中してほしいため、ナレッジ共有にかけるコストは最小限に抑えたいと考えています。
「今やっていることを共有するだけで良い」と伝えてはいますが、それでも準備が必要であり、できるだけ簡便にナレッジを共有できる仕組みを作る必要があります。
まとめ
ナレッジ共有は、チーム全体の成長を支える重要な取り組みであり、日々の業務に密接に関わる情報を迅速に活用できる環境を整えることは、業務効率化や属人化の解消に繋がります。
小規模で日常的な共有の仕組みを構築し、効率的に情報を管理・整理することが重要です。ドキュメント管理やナレッジの分類、アクセスのしやすさを意識することで、チーム全体が効果的に活用できる状態を作り出せます。
今後も改善を重ねながら、より効果的でスムーズなナレッジ共有の仕組みを目指していきます。ナレッジ共有を組織に定着させ、進化させるために、柔軟に調整し続けることが不可欠です。